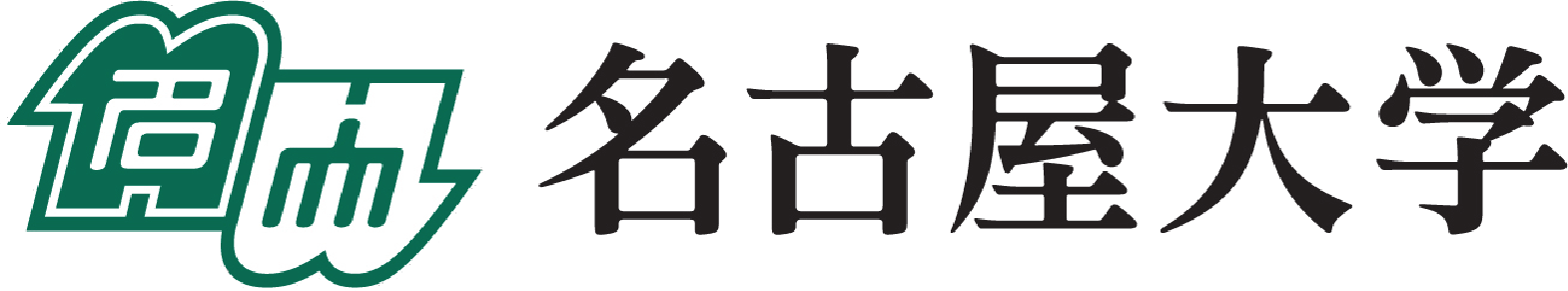施設について
先端的な遺伝子研究推進を目指して
施設長あいさつ
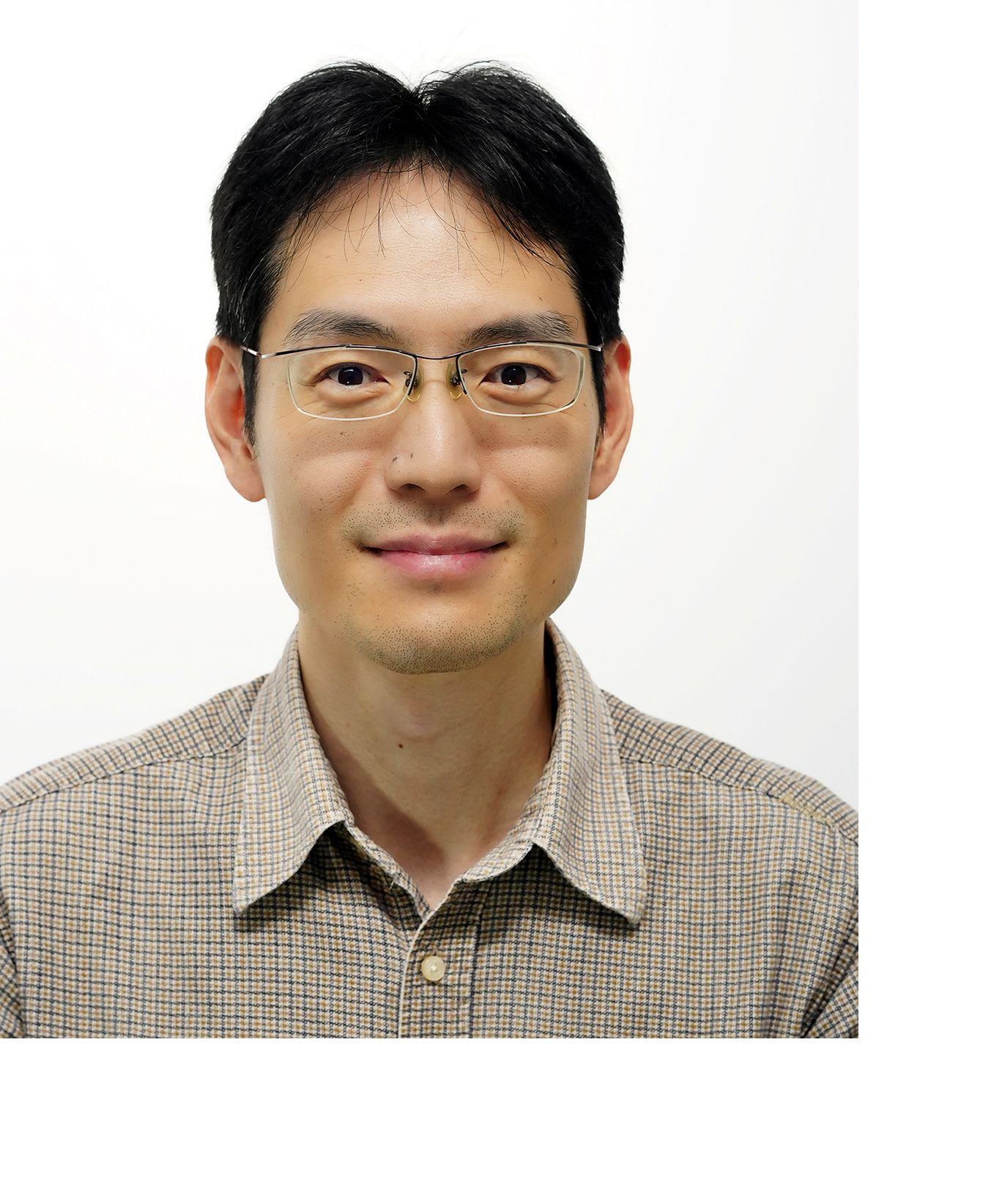
2025年4月より、前施設長・多田安臣教授の後任として遺伝子実験施設の施設長を務めております、打田直行です。本施設は、本学における遺伝子組換え実験の安全確保の中心となり、関連する設備を学内で共同利用できるよう提供すること、また、国際水準の遺伝子研究の中核拠点として、植物特有の生命現象に着目した重要な研究を推進することを目的に、昭和59年に創設されました。
1つ目の柱である共同利用機器・サービスの充実に向け、本施設では、大型高速遠心機などの汎用機器から次世代DNAシーケンサーなどの最先端機器まで、幅広い研究支援を行っています。学内外の研究者の利用を積極的に推進しており、特にキャピラリーDNAシーケンスサービスでは、近年低価格化の進む外注サービスにも負けない共同利用サービスを行うため、遺伝子実験施設職員の努力により、低価格・迅速な結果通知・サンプルの解析当日受付を実現し、学内60以上の研究室の年間約3万サンプルを解析しています。また、昨今の生命科学分野では、より大量のシーケンス情報を提供する次世代DNAシーケンサーによる解析が不可欠となってきている状況を受け、本学の卓越大学院プログラム「トランスフォーマティブ化学生命融合研究大学院」と連携し、2019年度より次世代DNAシーケンサーを用いた共同利用サービスも開始しました。これまでに学内の35以上の研究室が利用し、3000以上のサンプルを解析しています。こちらも低価格、高精度、迅速な結果通知に努めています。
もう1つの柱である高度な遺伝子研究の中核拠点としては、2014年に多田教授が着任し、植物の免疫応答に関与する遺伝子の機能についての研究を進めています。同研究グループには2018年から野元美佳博士が助教として加わりました(2023年に講師に昇任)。野元講師はロレアル-ユネスコ女性科学者日本奨励賞(2018年7月)や同国際新人賞(2019年3月)を受賞し、2022年からはさきがけ研究員としても活躍しています。同研究グループの研究の過程で、安価で簡便かつ大規模なタンパク質合成を可能とする新奇のin vitroタンパク質合成法を開発し、特許取得やNEDO・TCP2015最優秀賞を受賞しました。この手法を学内のより多くの研究者に利用してもらうべく共同利用サービスも開始しました。2020年4月には打田が新たに着任し、同研究グループには同年8月に前年の日本植物学会若手奨励賞を受賞した肥後あすか助教がさらに加わり、植物の形づくりと成長に関わる遺伝子の機能についての研究を進めています。また、2018年には、本施設の元助教授であり現在は理化学研究所・環境資源科学研究センター特別顧問の篠崎一雄特別先生が特別教授として着任され、以前から在籍されている杉浦昌弘特別教授とともに、先端的な遺伝子研究を推進しています。
近年の生命科学分野において遺伝子研究の重要性はますます高まっており、本施設は本学における遺伝子研究の中核拠点として学内の研究者の支援を強化し続け、本学の遺伝子研究推進により貢献したいと考えています。遺伝子研究の裾野が現在でもますます広がっていることを反映し本学においても遺伝子組換え実験の実施部局が増加する中、2025年4月には本施設の教員を中核とする形で学内小部局での遺伝子組換え実験の安全管理・審査をより着実かつ効率的に行うために遺伝子組換え実験合同審査委員会を新たに設置し、その運営も始まりました。本施設が学内構成員の遺伝子研究推進に十分に貢献できているのか、利用しやすい環境を提供できているのかを常に考えているところではありますが、さらなる貢献や改善に向け、皆様のご意見をぜひお聞かせください。
最後に、遺伝子実験施設の運営にご理解とご支援をいただいている名古屋大学および理学研究科の皆様に、心より感謝申し上げます。
2025年4月 遺伝子実験施設長 打田直行
遺伝子実験施設の概要
生物学はこの半世紀の間に劇的な発展をとげてきました。特に、近年のゲノム生物学の発展はめざましく、数年前には思いもよらなかったヒトやイネの全ゲノム情報が明らかにされました。名古屋大学においても理学、医学、農学、工学、考古学などの幅広い分野で、遺伝子やゲノムを基盤とする研究が活発に展開されています。
遺伝子実験施設は、本学における遺伝子組換え実験の安全確保の中心となり、関連する大型設備を学内の共同利用に供すること、遺伝子研究の中核拠点として先端的な遺伝子研究を推進することを目的として、昭和59年に創設されました。創設当初は現在の「遺伝子解析分野」の1部門だけで構成され、DNA合成やタンパク質のアミノ酸配列決定のサービスを全学的に行ってきました。また、研究面では、世界にさきがけて高等植物の葉緑体のゲノム構造を決定する等、現在のゲノム生物学の基盤となる重要な研究を展開してきました。平成11年度には、新たに「植物ゲノム解析分野」が設置され、既設の「遺伝子解析分野」と合わせて2つの研究分野体制に整備されました。「遺伝子解析」と「植物ゲノム解析」の両分野が相互に連携して、全国の植物ゲノム研究の中核拠点としての全国的業務や本学及び学外の研究グループの受け入れと支援を行っています。また、植物固有の現象でかつ生物科学上のインパクトの高い重要な生命現象を念頭においた国際的に水準の高い遺伝子研究やゲノム研究を活発に行っています。
なお、本施設の専任教員は創設当初より本学理学研究科の協力教員を兼任し、現時点では「遺伝子解析分野」と「植物ゲノム解析分野」がそれぞれ生命理学領域の「多細胞秩序研究グループ」および「植物分子シグナル研究グループ」として学部生や大学院生の受入れを行っています。具体的な研究内容については本施設や生命理学領域のウェブサイトなどを参考にしてください。
歴代施設長
- 中埜栄三(理学部教授)
- 1984.4~1986.3
- 杉浦昌弘(遺伝子実験施設教授)
- 1986.4~2000.3
- 小林 猛(工学研究科教授)
- 2000.4~2004.3
- 石浦正寛(遺伝子実験施設教授)
- 2004.4~2013.3
- 木下俊則(トランスフォ-マティブ生命分子研究所教授)
- 2013.4~2023.3
- 多田 安臣(遺伝子実験施設教授)
- 2023.4~2025.3
- 打田 直行(遺伝子実験施設教授)
- 2025.4~